ライター|國武悠人:NPO法人バーチャルライツ理事長。VR/メタバースに関連する政策分析などに従事。Twitter 記事一覧
※この記事は、ゲストライターによる寄稿記事です。おとな研究所編集部や所属ライターが作成した記事ではありません。なお、寄稿の応募はコチラから誰でも可能です。
4月26日、産経新聞が政府の「デジタル推進員」制度案に関する記事を公開した。
〈独自〉政府の「デジタル推進委員」制度案判明 5月下旬から募集開始、高齢者ら活用支援 – 産経ニュース
デジタル推進委員は、高齢者などデジタルに不慣れな人向けの講習会の開催やスマートフォンを使った行政の手続きに関してサポートを行う役職である。報酬は無く、任期は1年。政府は5月下旬からの募集を目指しているが、この制度案はSNSで激しい非難を浴びせられることになった。
しかし、筆者はこのデジタル推進委員制度が一定の成功を収めると予想している。
無給・薄給の公務員制度は存在
民生委員、児童委員、統計調査員という制度をご存じだろうか。どれも無給・薄給の特別職地方、国家公務員であり、主婦や地元の名士が就任している役職である。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-7.html
これらの委員は、無給・薄給にも関わらず社会的意義の高い事業に従事している。特に民生委員・児童委員は地域福祉の担い手であるソーシャルワーカーとして、精神的なタフさを求められる。デジタル推進委員にもとめられるそれよりも圧倒的にハードルが高い。
もちろん、既存の委員制度もサスティナビリティの観点から問題点が提起されているが、単にデジタル推進委員の成功、不成功の予測を論じるのであれば、現行制度が今日まで維持されている事実は無視できない。

写真は写真ACより(編集部)
目標1万人は現実的な数値
デジタル推進委員について政府は1万人を任命の目標としていることについても「無給の募集に人が集まるわけがない」といった批判が存在する。
しかし、目標1万人は非常に現実的な数値である。前述の民生委員・児童委員は全国で22万人が任命されているため、単純な数値の比較だけでも現実的な水準である。
また、民生委員・児童委員は地域の実情を深く理解している必要があるのに対し、デジタル推進委員は講習を受ければ就任することが出来るとされているため、実現可能性は非常に高い。
叙勲・褒章の対象となる可能性
また、デジタル推進委員の活動が叙勲・褒章の対象となり、大きなインセンティブが発生する可能性がある。現時点でも、国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員、統計調査員等の事務)に尽力した場合は藍綬褒章や春秋叙勲(瑞宝章等)の授与対象となることが、このような活動に参画するインセンティブとなっている。
任命の基準が課題
ここまで、なぜデジタル推進委員が成功するかを述べてきた。しかしこれは制度自体の成功を肯定しているのであって、当然、予想できる課題点も存在する。まず選考側が適切な人材を任命できるのかといった問題がある。
下手をすると情報商材系インフルエンサーが「デジタル大臣任命デジタル推進委員」の肩書を利用して高齢者を騙すことも考えられるほか、社会的なバックグラウンドの少ない人物が任命されることによって、何がトラブルが起きた際に「デジタル推進委員が事件に関与」といったセンセーショナルな見出しが使われる可能性がある。
終わりに
デジタル推進委員は岸田政権の目玉政策にしては珍しく攻めた政策である。果たしてこのままの制度で導入するのか、はたまた”万人受け”しそうな制度に変化していくのか。状況を注視していく。
ライター|國武悠人:NPO法人バーチャルライツ理事長。VR/メタバースに関連する政策分析などに従事。Twitter 記事一覧
※この記事は、ゲストライターによる寄稿記事です。おとな研究所編集部や所属ライターが作成した記事ではありません。なお、寄稿の応募はコチラから誰でも可能です。
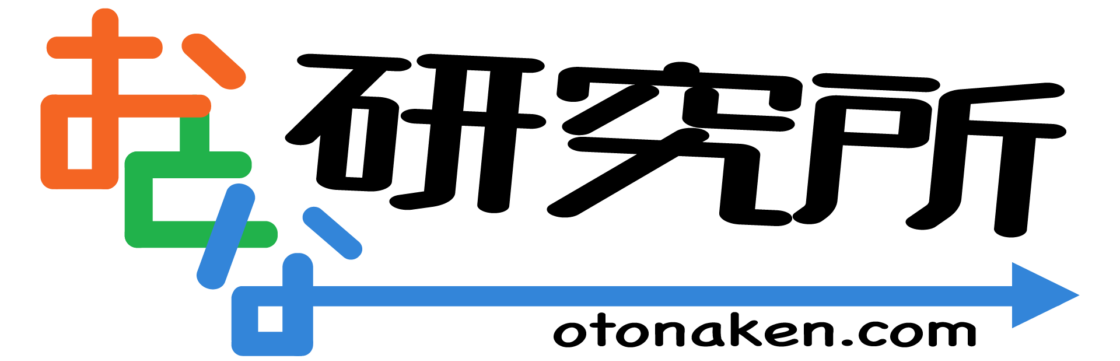
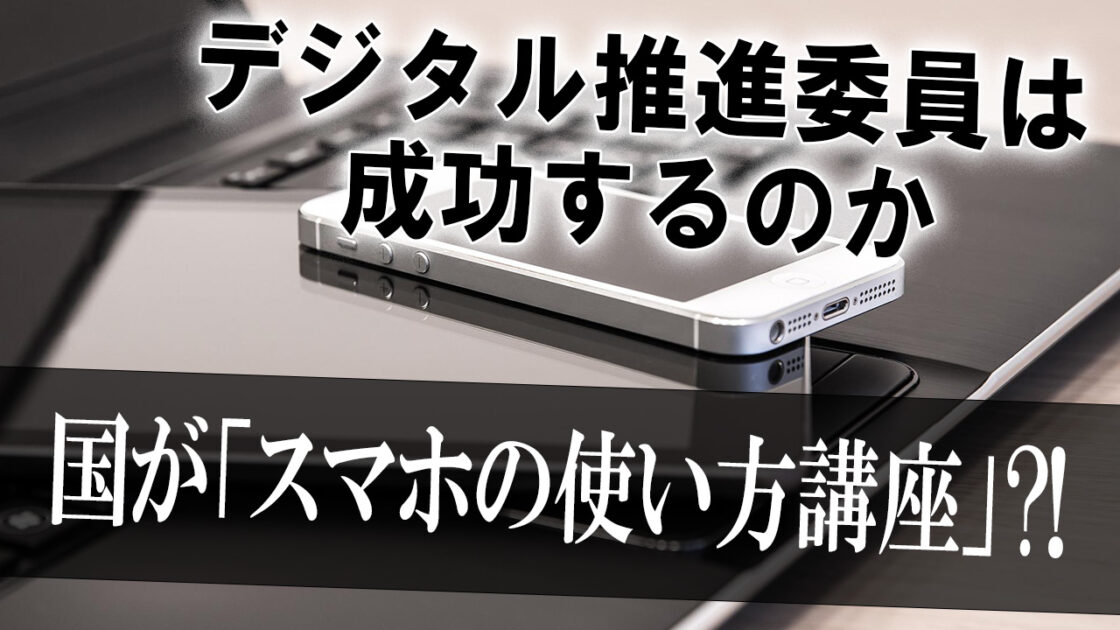
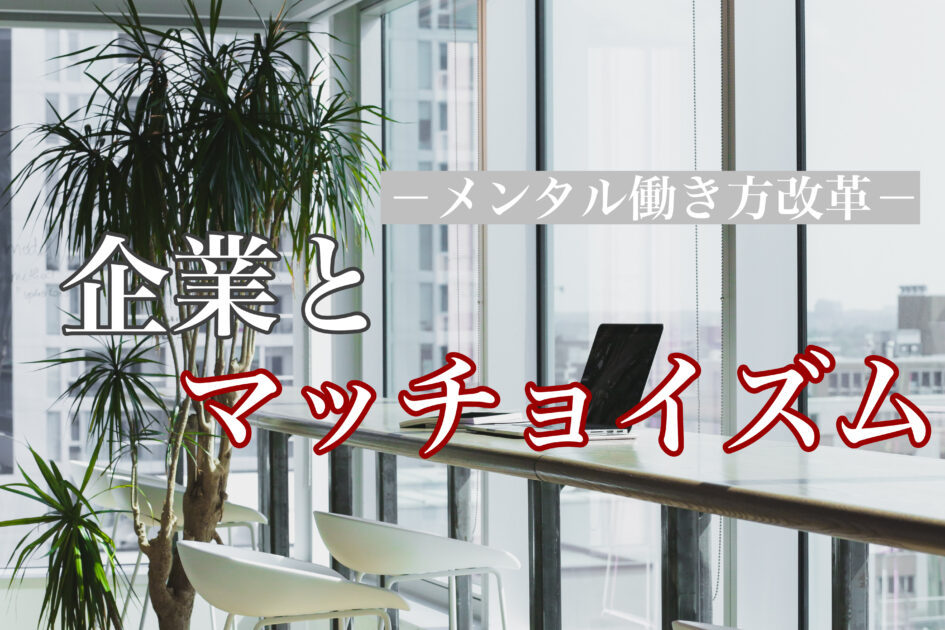
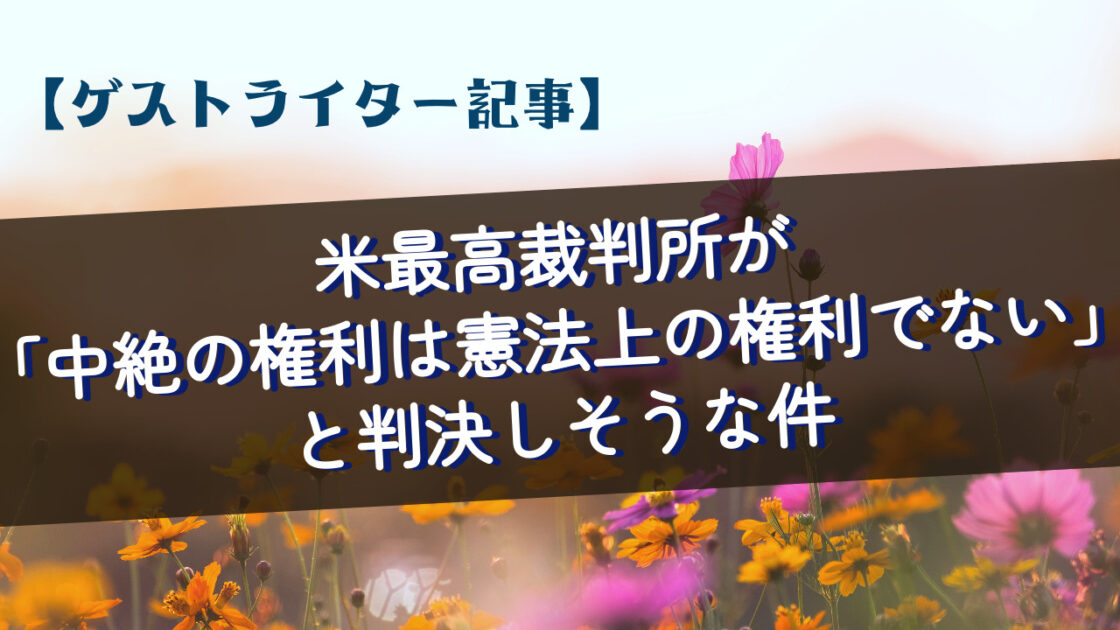
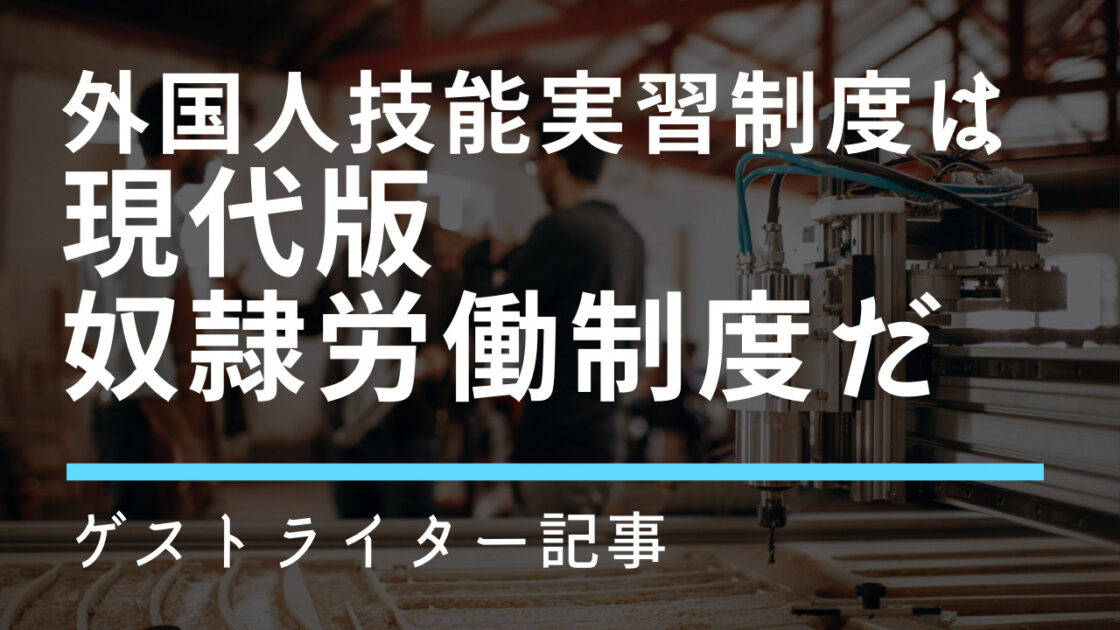







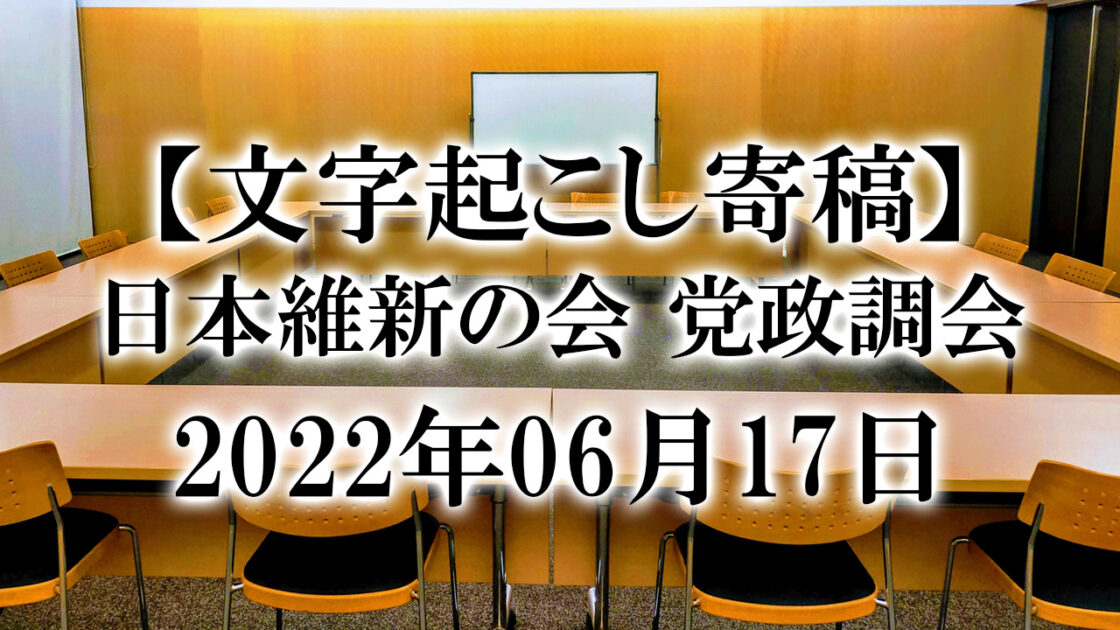

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。