大阪市の松井市長は、昨年11月の住民投票で否決されたいわゆる「大阪都構想」に代わる「総合区」の条例案を来年2月の市議会に提出する考えを表明した。

総合区制度は、現状大阪市内に24ある行政区を8つにまとめ、行政区よりも財源と権限を強化することで、住民サービスのさらなる拡充を図る。大阪都構想のように、特別区を設置する場合には住民投票で過半数の賛成が必要となるが、総合区は議会の過半数の賛成で設置が可能である。
いったい、都構想の簡易版といえる総合区制度でなにが変わるというのか。実現に持ち込むことはできるのか。
総合区と特別区の違いは? 今と何が変わるのか

昨年否決された特別区制度(大阪都構想)の簡易版ともいえる総合区制度。住民サービスの拡充を図るというが、具体的にどう変わるのか。
まず、行政区(現在)の区長は任期のない一般職員という扱いだが、総合区の区長は任期4年の特別職員として扱われる。一職員である行政区の区長とは違い、総合区の行政に関して一定の権限が与えられ、住民ニーズに沿った施策を実現させるねらいがある。予算に関しても、市長に提案することが可能だ。
行政区自体、住民のニーズにきめ細やかに対応するために設置されたものであるが、総合区とすることで、より一層住民のニーズに応えやすくなるという主張だ。特別区(大阪都構想)には劣るが、現状可能な範囲で最大限の制度改革といえるだろう。
果たして可決できるのか
大阪市議会は定数83。維新会派は40名であり、単独では過半数に届かないことから、他会派の協力を仰ぐ必要がある。
しかし、公明党は前回、松井市長が提案の動きを見せた際には賛同せず、提出を見送らせた経緯があるなど、今回も協力を取り付けることができない可能性がある。
比較的維新に親和的である「自民・市民・くらし」も「都構想にかわる制度の議論を進めたい」としていたが、代表の太田氏が「8区案ではダメだ」と反対する考えを示した。
今回の総合区案が否決されれば、改革は再び先送りとなることなり、維新が目指す地方分権の道が遠のいてしまう。それは何としても避けたいところだろうか。今まさに、松井市長は岐路に立たされている。
参考資料
・大阪市の24行政区→8総合区 松井市長、議案提出方針 – 朝日新聞
・大阪市会
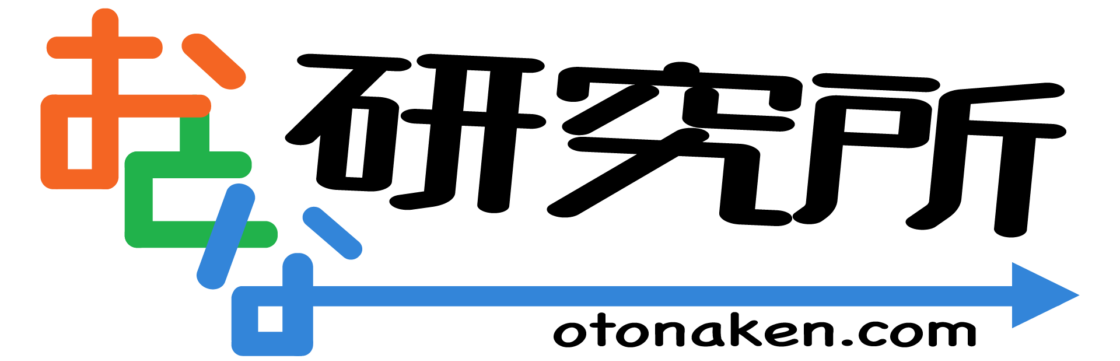
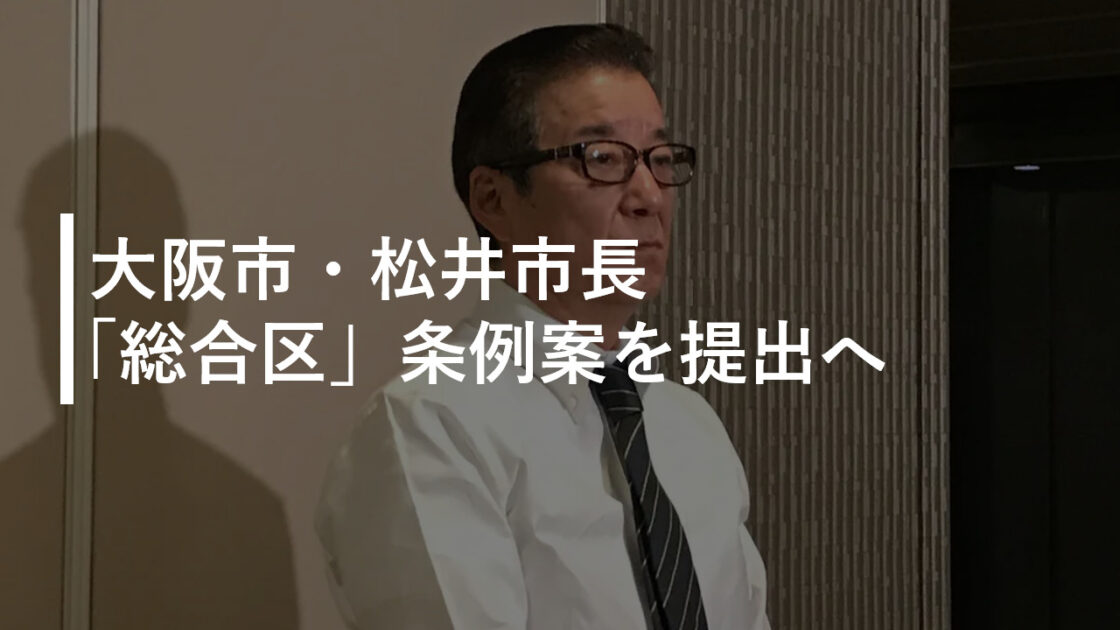
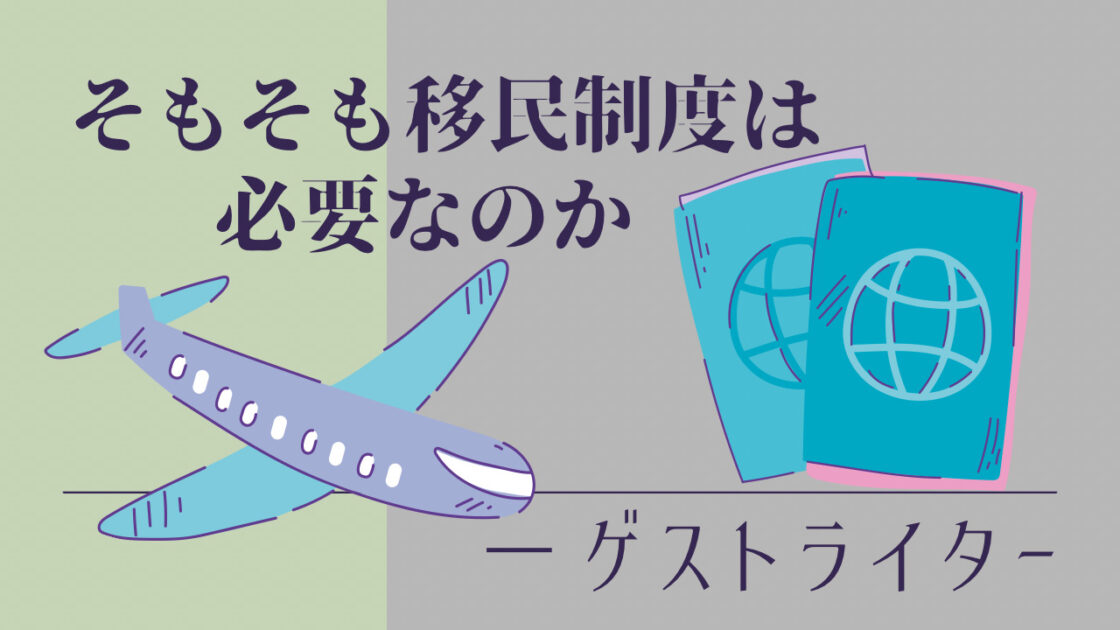
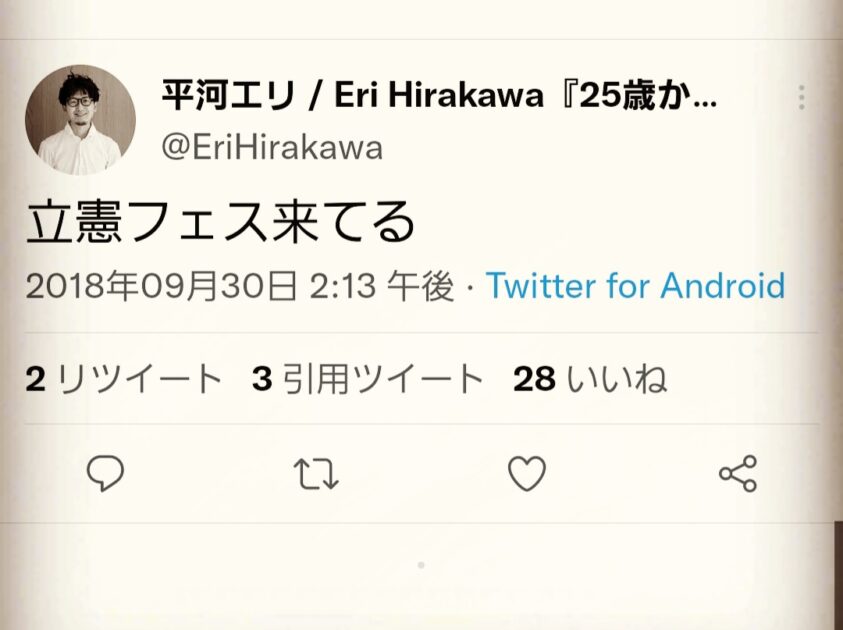




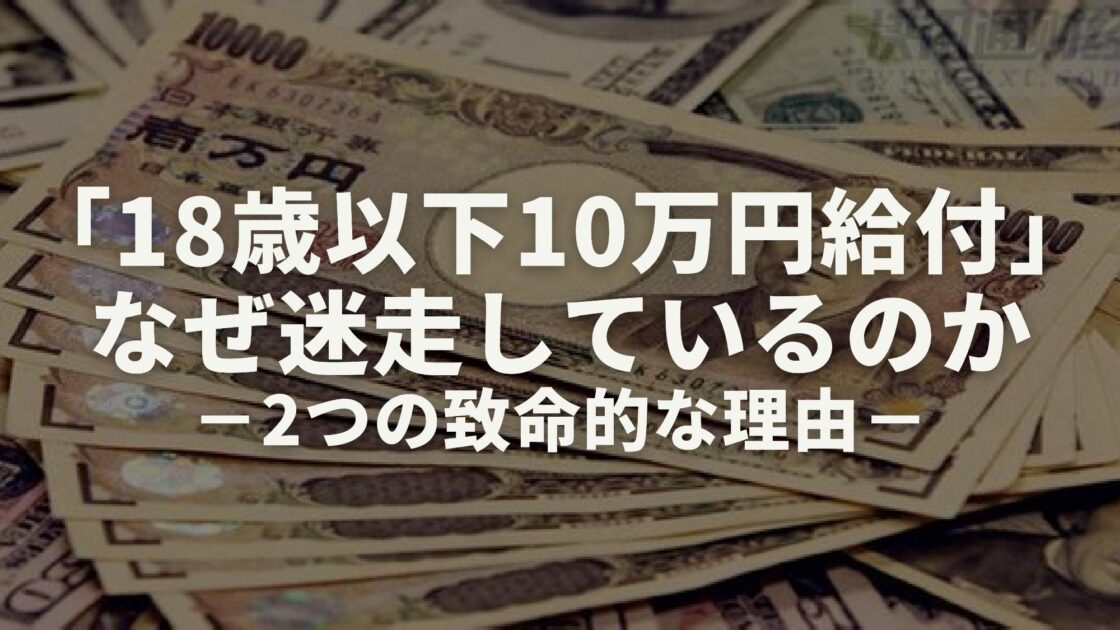



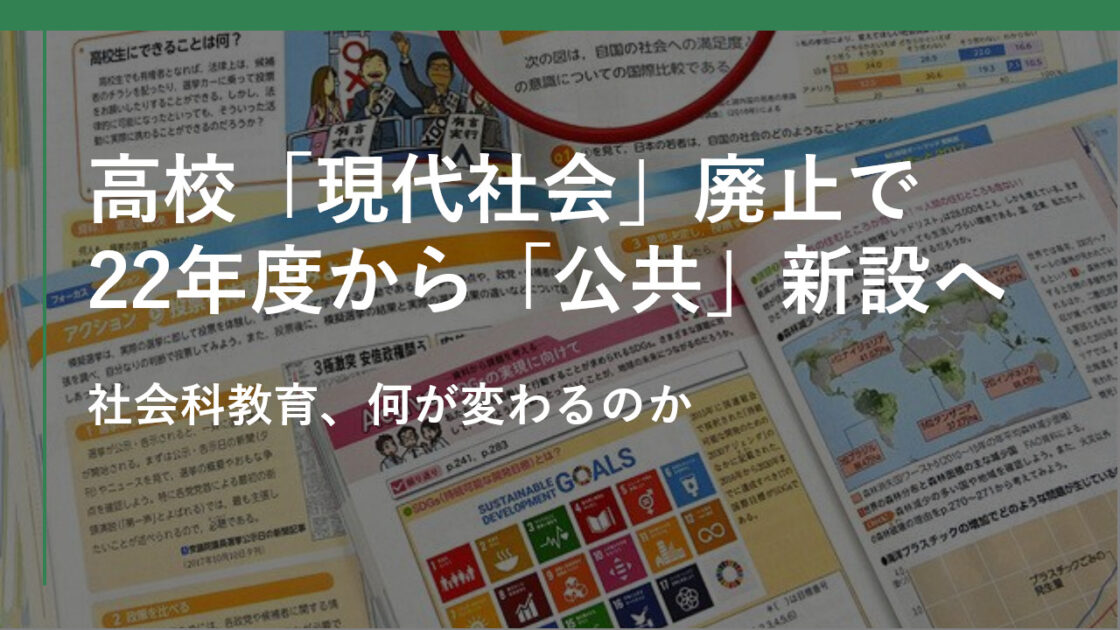
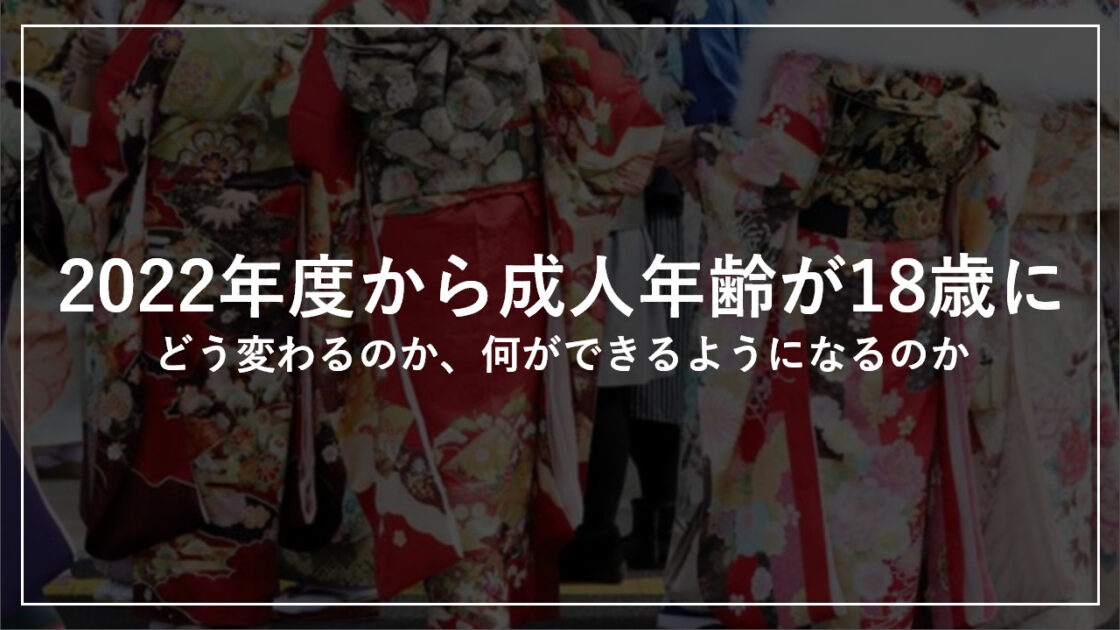

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。