オーストラリアは太平洋州最大の民主主義国家であり、日本とも基本的価値観を共有する国である。オーストラリアは大英帝国によって入植された歴史から、日本と同じくウェストミンスター制度(立憲君主制の下に2院議員内閣制)を採用している国家である。その為、これから説明する議会制度は日本の国会と似ているところが多い。
前回はオーストラリアの下院、衆議院の説明を行ったので、この記事を読む前に是非そちらを拝見してほしい。
オーストラリアにおける上院は米国と同様、「元老院」(Senate,セネット)と呼ばれており、各州の代表が下院衆議院で可決された法案の審議を行える。しかしながらウェストミンスター制度の大半とは異なり、元老院の採決を衆議院側で覆す事は不可能であり、予算を伴わない法案提出権は衆議院を同等である。
元老院の選挙区は人口別に配分される訳ではなく、各州には12議席(選挙毎6名選出)と準州には2議席が配分され、地域代表としての側面が非常に強く、(これは西オーストラリア(当時は独立した英国自治領)が連邦参加に対する条件としと事柄)人口が比較的少ない州に優位な構造となっている。(中でもタスマニア州内では下院よりもボーダーが低いため、泡沫無所属がたびたび当選する事態となっている)
| 州 | 前回選挙のクオータ | ニューサウスウェールズ州クオータとの比率 |
| ニューサウスウェールズ州 | 670,761 | 1 |
| ビクトリア州 | 534,207 | 0.8 |
| クイーンズランド州 | 414,495 | 0.62 |
| 西オーストラリア州 | 206,661 | 0.31 |
| 南オーストラリア州 | 156,404 | 0.23 |
| タスマニア州 | 50,285 | 0.07 |
元老院議員の任期は基本的に6年であるが、準州(北部準州、首都特別地域)選出の4名の任期は設定されておらず、衆議院選挙と同時に行われる。慣例上、衆議院の解散は元老院選挙と同時に行われるが、元老院議員の任期はその年の7月1日からと決まっているため、選挙日程によっては選挙直後の国会会期中に元老院議員の「入れ替え」が行われる場合もある。

更に、会期中衆議院から提出された法案2本が否決若しくは衆議院の同意なき修正可決から3か月経過した場合には総理大臣は総督に元老院の解散総選挙を求める事が可能であり、選挙直後の審議には両院合同審議による法案可決も可能となる。
選挙制度
元老院議員は各ブロック(州・準州)における単記移譲式比例代表制によって選出される。これは、有権者が党又は候補者の選好順序を投票用紙に記する事で死票を排除する制度となっている。

この選挙制度で当選するには候補者が「クオータ」相当の得票数を確保しなければならない。1クオータ相当の得票数は(有権者数÷クオータ数)+1で求められる。選好投票の通り、最下位の候補者は排除され、彼に投票した有権者の二位票が加算される。(詳しくは上記下院に関する記事を確認してほしい)
有権者が候補者を選好順に記した場合、有権者が望む順番で票が流れるが、政党の選好順序を並べた場合、政党が指定した党内候補者順に票が流れる仕組みとなっている。
更に、必要クオータ以上(余剰票)を獲得した候補者の票は再配分される。これはその候補者に投票した有権者の二位票の比率を余剰票を掛けた積が他の候補者に渡る事となる。
このプロセスはクオータに達する候補者が必要人数選出されるまで続けられるため、開票作業は一日では終わらないのが基本だ。
オーストラリア上院選挙制度の運用例
投票総数:180
当選者数:2
クオータ:91票
1.)一位票の集計
| 一位票(a) | |
| A候補 | 111 |
| B候補 | 23 |
| C候補 | 9 |
| D候補 | 37 |
結果:A候補の当選確定、20票の余剰票(101-91)の配分開始
2.)余剰票(総数20)の集計
| 一位票(a) | A候補投票者二位票 | 余剰票分配(b) | 投票総数(a+b=c) | |
| B | 23 | 67 | 13.07 | 36.07 |
| C | 9 | 12 | 2.38 | 11.38 |
| D | 37 | 22 | 6.55 | 43.55 |
結果:C候補の落選確定、C候補の2位票(A候補投票者の内C候補が二位票だった票の3位票含む)の配分
| c | 「C」の二位票(d) | Aからの再配分 | 余剰票再配分配(e) | 得票総数 (c+d+e=f) | |
| B | 36.07 | 8 | 8 | 1.59 | 45.66 |
| D | 43.55 | 1 | 4 | 0.79 | 45.34 |
結果: 最低得票者のD候補者が落選確定
D候補者の2位票は全て(唯一残っている)B候補者に配分、45.66+45.34=91で、結果クオータ(91票)を達成、B候補の当選確定。
この様に、単記移譲式投票制度の場合、複数人区であっても共倒れなどが起きにくく、比例代表制度に近い制度となっており、「候補者を選べる比例代表制度」と呼んで差し支えないであろう。筆者個人的には日本で行われている複数人区はこの制度に移行すべきだと考える。
次回は英国の選挙制度について説明していきたいと思う。
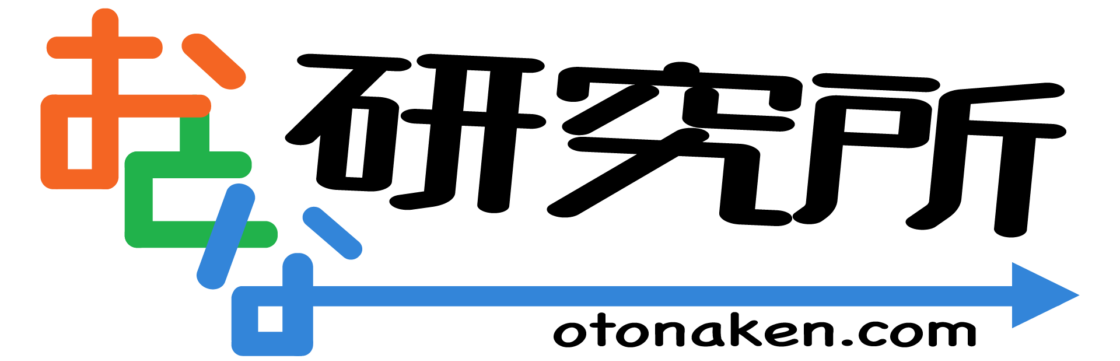


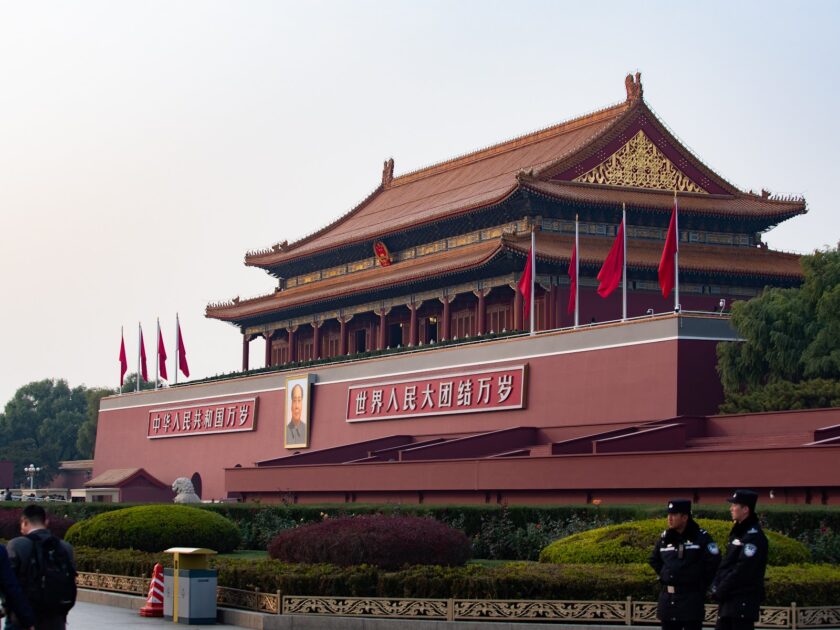



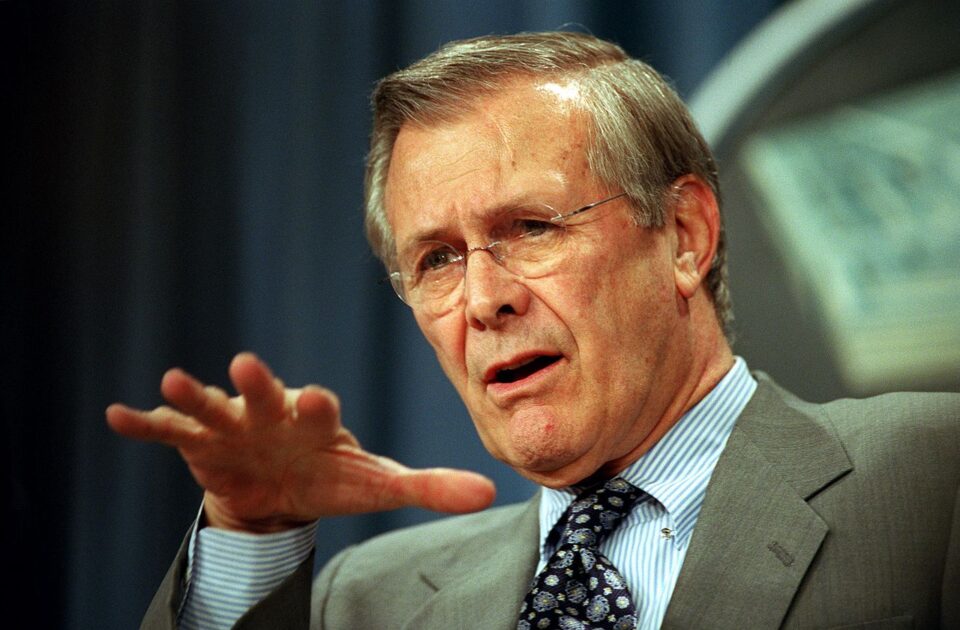
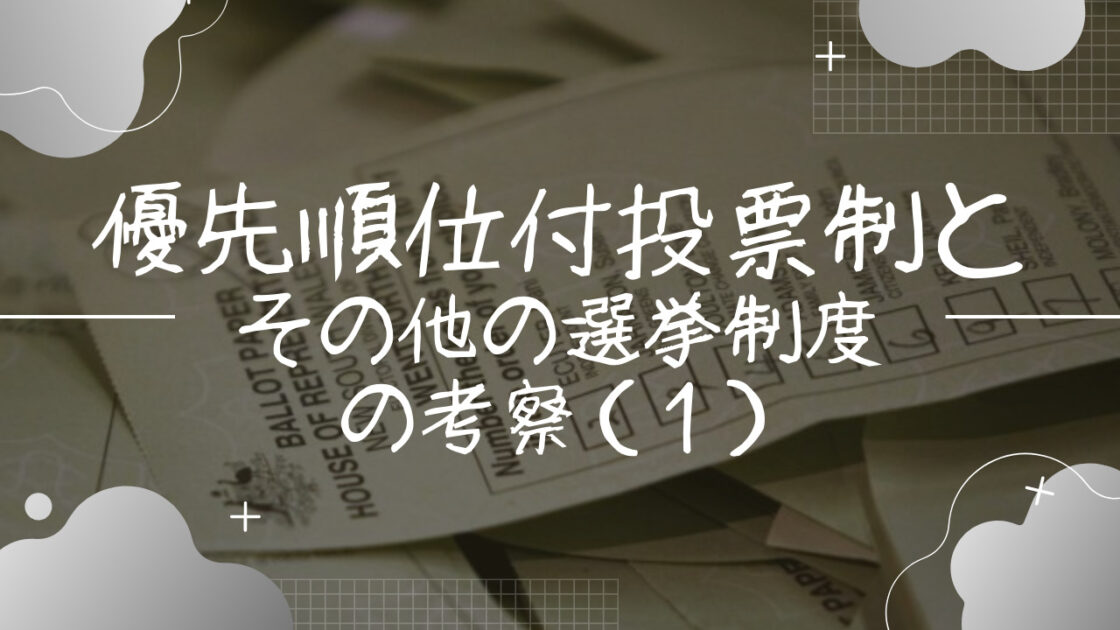




コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。